大町市に魅力を感じ、Iターン・Uターンして地域に根ざした仕事に従事されている
皆さんや、大町市の地域資源を活用した仕事を起業された皆さんを紹介します。

晩秋になると新酒ができたことをお知らせする杉玉が酒蔵の軒先を飾ります。
北アルプスの麓に位置する信州大町では、寒冷清澄な気候風土に育まれ、三軒の酒蔵が清酒を醸し続けています。酒造りの伝統と文化を支える杜氏さんは、三蔵とも他県から来たIターンの若手の皆さんです。今回は、その三蔵の杜氏さんたち(市野屋商店の村山大蔵さん、薄井商店の松浦宏行さん、北安醸造の山崎義幸さん)にお集まりいただき、お話を伺いました。
――杜氏さんというのは、お酒を造る現場の一番の責任者で、とてもやりがいのあるお仕事だと思いますが、皆さん杜氏になるために大町にいらしたのですか?

薄井商店(白馬錦)の松浦さん
松浦さん 僕は酒造りをしたくてこちらに来ました。
――実家が酒蔵なのになぜ大町へ?
松浦さん 実家は小さい酒蔵で兄が杜氏兼社長を務めています。一つの蔵に2人は要らないので、僕は初めは弁護士を目指していたのですが、やはり自分はお酒が好きで、うまい酒を造りたいという思いが強くなり、この世界に入りました。
といっても、実家に行っても仕事はないし、どこかの蔵に入りたくて就職活動をしましたが、実家が酒蔵ということでなかなか入れてもらえず、まず広島醸造研究所に入ったんです。そうしたら、白馬錦の前の杜氏さんと研究所の先生がつながりがあって、ここを紹介してもらいました。
――大町にと言われてどう思いましたか?
松浦さん 酒造りのためには温かいよりは寒い方がいいとは思っていましたが、最初はすごく寒いぞと脅かされましたね。黒部ダムのイメージしかなく、山奥だと思って来たら意外と町中でした。12年前のことです。その時は村山さんが先輩として白馬錦にいらして。

市野屋商店(金蘭黒部)の村山さん
――村山さんはいつ大町にいらしたんですか?
村山さん 19年前、28の時です。住み込み食事付きの求人情報に引かれて、千葉から来ました。関東の求人情報誌にこちらの求人が出ていたんです。当時は蔵人も50代中心で若い人がいなかったんですね。なぜか当時、長野県中の蔵が高齢化していた時期でした。
――それでは、仕事は何でもよかったけれど、たまたま蔵人だったということですか?よく飛び込む決意をされましたね。
村山さん そのときは年間雇用で、夏は食事はないけれど酒蔵※1に住んでいいよと言われて。夏は住んでいるのはオレだけ、オレの家(笑)。結局結婚する1年前くらいまで住んでいました。
(※1:冬の間泊まり込みで酒造りができるように、酒蔵には隣接して宿舎がある。)
――山崎さんはもう少し後にいらしたんでしたっけ?

北安醸造(北安大國)の山崎さん
山崎さん 長野県にはいたんですけどね。学生が終わってから、東京にいたり名古屋にいたりカナダにいたり…。コンピューター関係の仕事をしていました。山登りが好きでいろいろな山を歩いていたんだけど、どうせならこっちに住んだ方がいいかと思って。たまたま建設会社の求人があったので白馬に移って来たんです。白馬では5年くらい建設会社にいたけれど、建設会社もだんだん景気が悪くなってきて。大町のアパートに住んでいたんですが、たまたま近くの酒蔵で求人があったので応募しました。
――大町の三蔵を担う杜氏さん、お三方ともが、そんな偶然に導かれて大町にいらしたなんて、運命的なものを感じますね。最初から杜氏として採用されたんですか?それとも、蔵人で入って、だんだん昇格していくのでしょうか?
山崎さん 最初から杜氏になることが約束されていたわけじゃなかったけれど、若手が一人しかいないんだから競争相手もいないし、最初から決まっていたようなものだったかな。「自分がやらなきゃ誰がやるんだ」と。
――そろそろ仕込みが始まっているんですよね。始まれば泊まり込みで付きっ切りですか?
松浦さん 11月から3月いっぱいまでは酒造りですね。始まったら予定が詰まってしまいます。
村山さん 昼間は息抜きができるけど。朝は仕込みが忙しくて、夜は作業だし。
山崎さん 長い仕事だよね。酒造りは温度管理が重要で、基本的には4〜5度の室温の部屋で作業をするけれど、麹室は室温が高くて温かい。寒暖の差があると疲れます。
村山さん 丈夫でないと勤まらないよ。蔵人になっても辞めていく人も多い。
――それでは次に、お酒を造る上での、こだわりなどはありますか?座談会では伺いにくいのですが(笑)。村山さん、蔵によってやっていることは違うのでしょうか。
村山さん 基本的には同じです。やりたいこと、やろうとしていることは同じ。おいしいお酒を造ることです。どうしてくれとは社長も言わないし、任せてもらっています。
山崎さん まあ、いろいろ注文されても困るんですが。
村山さん 場所や設備が違えば、味はどうしても違う。あるものの中でやれることをやろうと努力しています。
――味の違いはどうやって出しているのでしょう。
松浦さん 原料を変えたり、精米割合を変えたり。同じように仕込んでも、タンクごとに多少は違います。品質を一定にする必要があるので違うタンクをブレンドすることもあります。
山崎さん ブレンドもあるけど、少量多品種の時代だからね。1つの銘柄に1つのタンクということもめずらしくない。
――少量多品種ということになると、それぞれの銘柄の違いを、翌年も同じように出さなければならないですよね。それって、神業じゃないですか。
松浦さん 同じ味は無理ですね。
山崎さん 違ってもあまり分からないけどね。同じ車種の車で形が違ったら問題だけど、お酒は形のないものだから。
松浦さん よくできたものを取っておきたくても、それも味が変わってしまいます。
山崎さん 年が経つと違う味になっていくので、あえて古酒にすることもあるよね。
――なるほど、雪中埋蔵のように、保管する場所や温度によっても違いますよね。奥深い世界ですね。お水へのこだわりはどうですか? 市野屋さんは氷筍水を使っていらっしゃいますよね。
村山さん 氷筍水もやっています。氷筍水の採水場所は扇沢※2ですが、元は関電トンネルの中の破砕帯の水だそうです。
(※2:立山黒部アルペンルートの長野県側の起点となる駅。ここから黒部ダムに向けトロリーバスが出ている。)
山崎さん 水だけでは、飲んで明らかに分かるような違いを出すのは難しいかな。
村山さん それでも、長野県の酒と山を挟んだ向こうの酒は結構違いますよね。
山崎さん 飯田とか南の方ともまた全然違います。県内だけでも水は全然違う。
村山さん 生水で比べるよりも、酒で比べた方が違いが分かるかもしれません。
――お米へのこだわりもありますか。
松浦さん うちでは全量、市内の契約栽培農家のお米を使っています。
村山さん うちも今年は全量契約栽培の米になりました。大町産のトドロキワセと美山錦。全部そうしようと思ったわけではなく、仕込み量が減っているので契約量で賄えただけですけど。
松浦さん 僕はやらないけど、二人は自分で米作りからやってる。それはこだわりですよね。
村山さん 夏は比較的暇だからね、酒米も飯米もやっています。今は田んぼが市内のあちこちに散らばっていて大変です。全部回ったら20kmくらいある。前は、田んぼを借りるのが大変だったけれど、だんだん頼まれる田んぼが増えてしまって今は6町歩くらいやっています。いい機械を借りられれば大変じゃない。時間はかかるけどね。田植えも草刈りも何とかなっています。
――では、お酒造りの上で、大町の魅力って何でしょうか。
村山さん 寒いから冷やすのに楽です。酒造りは室温が4〜5度くらいでないといけないので。
松浦さん 温かい地域は電気で冷やしているんです。
村山さん もともとお酒は寒いところの物ですね。鹿児島や沖縄には日本酒ってないですよね。
山崎さん 先ほどから話に出ているとおり、おいしいお水があって、いい酒米がとれて、寒い気候があって、いい条件が揃っていますよね。
村山さん 水がきれいだと、それで育つ酒米もおいしくなります。
(後編に続く)

キレ良くスッキリのやや辛口
企業情報
- 会社名
- 市野屋商店
- 代表者
- 社長 福島 敏雄
- 創業
- 慶応元年(西暦1865年)
- 郵便番号
- 〒398-0002
- 住所
- 長野県大町市大町2527番地イ号
- 電話番号
- 0261-22-0010
- ファックス
- 0261-22-0006
- Eメール
- お電話またはファックスで
- ウェブサイト
- http://www.ichinoya.com/

甘辛のバランスの良い味わい
企業情報
- 会社名
- 株式会社 薄井商店
- 代表者
- 社長 薄井 朋介
- 創業
- 明治39年(西暦1906年)
- 郵便番号
- 〒398-0002
- 住所
- 長野県大町市大町2512-1
- 電話番号
- 0261-22-0007
- ファックス
- 0261-23-2070
- Eメール
- ホームページのお問合せフォームにて
- ウェブサイト
- http://www.hakubanishiki.co.jp/
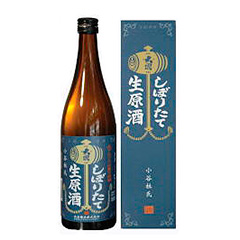
お米本来のおいしさが際立つ甘口
企業情報
- 会社名
- 北安醸造株式会社
- 代表者
- 社長 伊藤 敬一郎
- 創業
- 大正12年(西暦1923年)
- 郵便番号
- 〒398-0002
- 住所
- 長野県大町市大町2340-1
- 電話番号
- 0261-22-0214
- ファックス
- 0261-23-4834
- Eメール
- hokuan@dhk.janis.or.jp
- ウェブサイト
- http://www.dhk.janis.or.jp/%7ehokuan/
中心市街地の狭い範囲に3つの酒蔵が集まっています。
蔵元3社の所在地
次回は、酒蔵3社(市野屋商店、薄井商店、北安醸造)の
杜氏さんのお話(後編)を紹介します。






