更新日:
令和7年7月
令和7年7月1日 国勢調査2025 大町市本部設置

7月1日、市は令和7年国勢調査大町市実施本部を設置しました。
実施本部は、矢花副市長が実施本部長を務め、国の最重要調査である国勢調査を実施します。
市内(国内)に住んでいる人は全員が対象となり、調査員が全世帯を訪問します。矢花実施本部長は「国勢調査は法令・施策のベースとなる統計。ぜひ調査にご協力いただきたい」と話しました。
回答はインターネットでも可能ですので、ぜひご協力ください。
令和7年7月7日 レゾナック・グラファイト・ジャパンさまから大町南小へ寄付をいただきました
7月7日、(株)レゾナック・グラファイト・ジャパンさまから大町南小学校へ、金10万円を寄付いただきました。
この寄付金はレゾナック・グラファイト・ジャパンの従業員が行っているアルミ缶の回収の収益で、閉校する小学校の閉校行事への寄付です。
レゾナック・グラファイト・ジャパン事業所長の河浪健一さんは「南小は歴史ある学校。南部小としての次の一歩を踏み出すため、地元の企業として応援したい。南小が思い出に残るように有効に使って」と話し、南小児童会長の橋本菖(あやめ)さんは「南小の全校を笑顔にするために使わせてもらう」と感謝しました。


令和7年7月8日 柳家圭花さん 真打昇進を市長へ報告
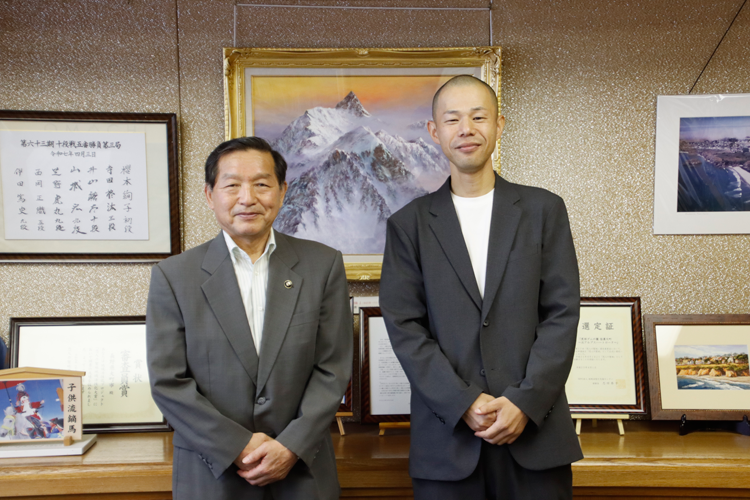
7月8日、落語家の柳家圭花さんが大町市役所を訪れ、牛越市長へ来年の3月の真打昇進を報告しました。
圭花さんは、大町大黒町の出身で落語協会に所属しています。29歳の時に落語協会に所属し、平成24年に前座、平成28年に二ツ目に昇進しました。真打への昇進は落語協会の理事会が、実力を見て決定しており、毎年4~5人が昇進するそうです。圭花さんには4月に師匠の柳家花緑さんから電話で昇進が伝えられましたが、圭花さん自身も「そろそろかな…(笑)」と思っていたそうです。大町市出身の真打は圭花さんが初です。
当日、地元の支援者の皆さんと市役所を訪れた圭花さんは「今までの応援に感謝。今の現状に満足はしていない。急にうまくなるわけではないので、今までの積み重ねを披露していきたい」と昇進に向けた抱負を語りました。


令和7年7月9日 自衛官募集相談員委嘱状交付式
7月9日、大町市役所で自衛官募集相談員委嘱状交付式が行われました。
自衛官募集相談員とは、自衛隊地方協力本部が実施する募集のための広報活動に協力する人で、市区町村長と地方協力本部長の連名で委嘱されています。当日委嘱されたのは、市内の奥原喜義さんで、奥原さんは3期目の相談員となりました。
長野地方協力本部長の山口敦史さんは委嘱にあたり「日本を取り巻く安全保障環境は依然として厳しい。国民の生命・財産を守る自衛官の魅力を引き続き伝えてほしい」と話し、奥原さんは「大町病院勤務なので地域防災の観点から自衛隊に協力したい」と話し、大町市へもイベント時のブース設置など協力を求めました。

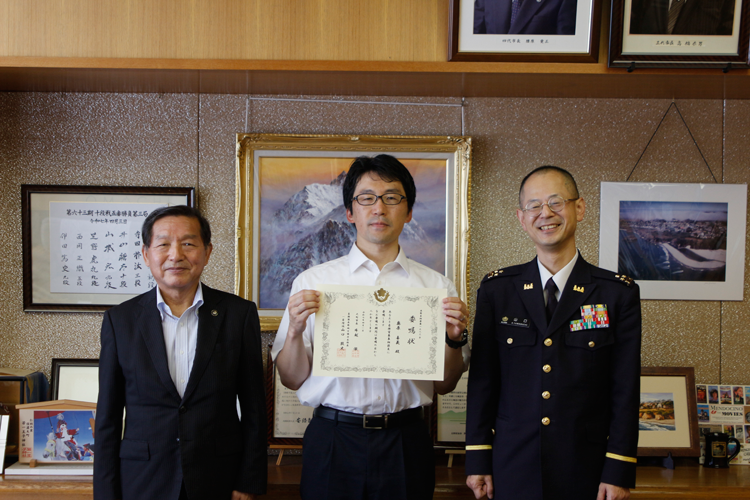
令和7年7月10日 美麻新行水車小屋ワークショップ
7月10日、美麻地域づくり会議は、美麻新行地区の水車小屋でワークショップを開催しました。
新行地区のシンボルになっている水車小屋ですが、経年劣化によりかやぶき屋根のふき替えや、ぐし(屋根の頂上部分)の修繕が必要な状況になっています。業者に依頼すると1,400万円超かかる大規模な工事になってしまうため、時間をかけて美麻のかやを使ってワークショップを行い、修繕していくことになりました。
ワークショップには美麻小中学校の5年生・7年生や地域の皆さんが参加し、ぐしになる材木への防腐剤の塗布、実際に屋根に上ってかやのふき替えなどを行いました。作業の講師は美麻出身の渡辺拓也さん((株)縄文屋根)が務めました。渡辺さんは「イネ、ムギ、ススキ、屋根に使えば全部かや。ススキやヨシは30年くらい長持ちする」などかやについて児童に伝えました。
児童の皆さんは「屋根の上からの眺めがよかった!」「もっと居たかった!」など楽しい感想を話したり、防腐剤の耐久性やかやの寿命について渡辺さんに質問したりしていました。









令和7年7月19日 扇沢キッチンカー/山岳スタンドオープン
7月19日、広報担当者が少し早起きして山にまつわる2つの場所にお邪魔してきました。
扇沢駅 カクネバル
黒部ダムの玄関口、扇沢駅ではカクネバルさんがキッチンカー出店を行っていました。カクネバルは北安大国の蔵人の永澄悠太さんと祭さん(元大町市地域おこし協力隊)夫妻が営むキッチンカー。山が趣味のお二人ですが、かつて登山者として訪れた扇沢駅、夜行バスで疲れた体で温かいコーヒーでも飲めたら、と思ったのが出店のきっかけだそう。出発前の登山者や電気バスを待つ人に温かいものを、ということで早朝から出店し、蔵人ならではの酒かすやこうじを使ったメニューや杜氏が焙煎した豆を使ったコーヒーを提供しています。
祭さんは「これから山に向かう人に、温かいコーヒーとおいしいパン、甘酒で作ったトレイルバーでエナジーチャージして出かけてほしい」と話し、登山者を送り出していました。




信濃大町駅 まちなか山岳スタンド

まちなか山岳スタンドは、大町市地域おこし協力隊員を中心に運営する、登山者や立山黒部アルペンルートへの観光客へ向けた街中の小さなインフォメーションセンターです。登山客や登山バスに合わせて早朝からオープンし、山に関する情報発信や、山に関連するアイテムや行動食の販売を行います。
おしゃれなアイテムがそろっていますので、登山をしない人も立ち寄ってみてはいかがでしょうか。11月3日までの土・日曜日、祝日の午前6時~午後2時に営業しています。


令和7年7月22日 全国高校総体(体操・なぎなた)に出場する大町岳陽高の選手が表敬訪問

7月22日、全国高校総体に出場する大町岳陽高校の生徒が、牛越市長に出場を報告しました。
この日、市役所を訪れたのは、令和7年度全国高等学校総合体育大会の体操競技に出場する続麻世稀さん(1年)、米野めいさん(2年)、吉澤梨乃さん(1年)と、なぎなた競技に出場する伊藤千花さん(2年)、伊藤望さん(2年)、奥原夢さん(2年)、下川真由さん(2年)、荒澤柚子香さん(1年)、二木優衣奈さん(1年)の皆さんです。
体操は5月31日、6月1日に長野市で、なぎなたは6月1日に松本市でそれぞれ開催された県総体で優れた成績を収め全国への切符を手にしました。
体操の米野さんは「2回目の出場なので去年の反省を生かして全力で向かいたい。ミスを減らすことを意識してひとつひとつ丁寧にやりたい」、なぎなたの奥原さんは「県では満足な結果だった。予選リーグ突破を目指して頑張りたい」とそれぞれ大会に向けての決意を述べました。
令和7年7月25日 北アルプスブルワリーさまからライチョウ保護活動のための寄付をいただきました

7月25日、北アルプスブルワリーさまからライチョウ保護活動のため寄付金をいただきました。
大町の水で作られるクラフトビール「氷河ラガー」が北アルプスブルワリーの主力製品ですが、その缶にライチョウが描かれていることから、氷河ラガーの売上金の一部を寄付いただいています。寄付は令和5年から続き今回で3回目です。
北アルプスブルワリー専務の成沢隼人さんは「クラフトビールのための飲み歩き旅行なども増えてきていて、山博の入館者増にも貢献できると思う。今後ももっとビールで協力していければ」と話しました。
令和7年7月27日 市プロモ委オフィシャル広報パートナーにやぎちゃん就任
7月27日、大町市プロモーション委員会は、登山系ユーチューバーとして活躍している「やぎちゃん」をオフィシャル広報パートナーに委嘱しました。やぎちゃんは「山好きのアジト」を作るために、東京から長野へ移住し、山の魅力を発信しているインフルエンサーです。(YouTube登録者数11.9万人[令和7年8月時点])
委嘱式はやぎちゃん主催のツアーに参加したファン30人と一緒に室堂のホテル立山で行われました。
やぎちゃんは「アルペンルートは、5カ月で30日以上訪れていて、うれしい気持ちでいっぱい。また、公式で情報発信できるのでやりがいにもなる」と話しました。




令和7年7月28日 JR東日本との大規模災害発生時における帰宅困難者対応に関する協定書 調印式

7月28日、大町市と東日本旅客鉄道株式会社(以下、JR東日本)長野支社は、大規模災害発生時における帰宅困難者対応に関する協定締結の調印式を大町市役所で行いました。
この協定は、災害発生時に帰宅困難者に対して、駅の構内を一時滞在場所として開放することを定めたものです。
JR東日本長野支社は、平成23年の東日本大震災の際に、多くの帰宅困難者が発生したことを教訓に、県内12自治体と同様の協定を締結しています。
同支社の北沢敏広所長は「利用者の命を守り、安全で安心な環境を提供したい」と話しました。また、牛越市長は「当市は、国内外から多くの観光客が訪れるため、支援をいただけることは大変心強い」と感謝を述べました。
この記事へのお問い合わせ
情報交通課広聴広報係
内線 404
E-mail: kouhou@city.omachi.nagano.jp
アンケート
より良いホームページにするため、皆さまのご意見をお聞かせください。
なお、お答えが必要なご意見等はこちらではお受けできません。問合せ先に電話またはメールでお願いします。